「あんなこと言わなければよかった」「ちょっと空気を悪くしてしまったかもしれない」と寝る前に思い出して落ち込むことはありませんか? わたしももれなくその一人です。
基本的に一人で作業をしているため、最近の仕事の相棒はAIになりつつあります。WordPressサイトを作りながら、デザインやコードの相談もAIとやり取りしています。たまに思った通りの回答が得られずイライラして、「全然違う」とストレートに文句を言ってしまっても、AIは怒らずに「別のアプローチを試しますね」と返してくれます。そのたびに「これ、人間相手だったら絶対こんな言い方しないよな…」と自己嫌悪に陥ります。
そんな日々の中、半年ぶりに美容室へ行きました。家族以外との会話はほぼゼロの日々を過ごしていたので、他人と1時間程度もおしゃべりを交わすことに不安があったのですが、美容師さんの巧みな雑談力のおかげで無理なく会話がつづいたのでした。
“雑談の型”を知る
“雑談力”というキーワードでたくさんのビジネス書や自己啓発本が出ているくらいですから、雑談に苦手意識を持っている人はたくさんいるのだと思います。
amazon prime readingで見つけたのは、『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける 』。雑談は“型”があり、その型を踏襲すれば誰でもスムーズに雑談をこなせるようになるハウツー本です。
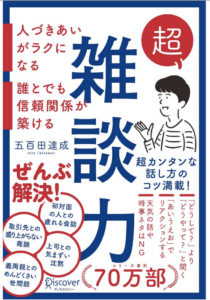
例えば、相手が何か話してくれたときに、それに反応して質問を即座に返すのがとにかく苦手、何を聞いたらいいかわからないという人は多いはず。わたしも、テンポ良く答えづらいような質問を投げたてしまったが故に、相手はうーんと考えはじめてしまい、そこで会話終了…なんてことがしばしばあります。
§
ここで使える「雑談の型」は、howで聞き返すということ。どうやって、どのくらいといった手段や程度を訊ねる質問は比較的答えやすい。
✔︎ 手段や方法のhow
- 「週末富山旅行に行ったのよ」
- 「へ〜いいね、どうやっていったの?車?新幹線?」
- 「車で行ったよ。高速で渋滞にハマちゃってね…」
✔︎ 程度のhow
- 「風邪ひいちゃってさ」
- 「あら大変、どのくらい前から?」
- 「一週間くらい前かな、なかなか良くならないよ」
さらにNGパタンとしてよくやってしまいがちだと気づいたのは、 whyで相槌を打つこと。すべてのことにこれといった明確な理由があるものではないと書かれていてハッとしました。
- 「うちの子ども、すごく短気なんだよね」
- 「え〜そんなふうに見えないけど、なんでだろうね… 多感な時期だよね…」
また「なんでそんなことしたの」と子どもを叱りつけてしまうと萎縮してしまうように、なんで?と理由を聞かれるってなんとなく問い詰められているような感覚を与えてしまうというのも納得です。反対に、子どもになんでなんでとしつこく問われつづけるのもいい気分がしないですよね。
ママ友以上の関係になれないのはなぜか -少しずつの自己開示
最低限悪い印象を持たれなければOKというときは、「変化を指摘する+褒める」の型。褒められて腹を立てる人はいません。そして、褒めてもらったら謙遜せずに肯定する。なんとなく感じがいい人はみんなそつなくこの型ができていて、ポジティブなオーラに満たされています!
§
さらに盲点だったのは、「仲良くなりたい人には自分の話(自己開示)をしなければならない」ということ。当たり前と言えば当たり前なんですが、パーソナルな部分に少しでも踏み込まないと、関係は深まらないんですよね。
例えば保育園の保護者同士なら子どもの話にはじまって、今日も寒いね〜暑いね〜程度の当たり障りない天気の話などが共通の話題になるでしょう。 子どもの話は一見共通の話題に見えて、第三者の話題。それ以上掘り下げても親同士が仲良くなることは難しく、子どもを介さない“ママ友”以上の関係にはなれないのだとこの数年間の疑問が解決しました。「子どもの話題+少しずつの自己開示」の型が、打ち解けるポイントなのだと思います。
ここでの一番簡単な自己開示は“気持ち”を話すこと。嬉しい楽しい悲しい驚いたなどなど… 自分の心情を伝えると共感が生まれぐっと距離が縮まる……そんな経験を何度も重ねて友達を作ってきたような…学生時代が思い起こされました。
大人になってから友達ができない人へ
振り返ればこれまでの人生って、本書に書かれているようなたくさんのコミュニケーションを自然と積み重ねてきた気がするのですが、“型=フォーマット”としてあらためて言語化されると腑に落ちることばかり。
学校という集団生活を抜けてしまった途端に、今までできていたはずのことがスムーズにいかなくなっている……そう感じている人は、ぜひ本書から“雑談の型”を取れ入れてみては。

